【ChatGPT】研究テーマが思いつかない人向けのプロンプト

研究テーマは急に言われると思いつかないものです。
強引に思いついたとしても、特に興味のないものだったりもします。
そういう時にはChatGPTを使いましょう。

INDEX
研究テーマのアイデアを出すプロンプト
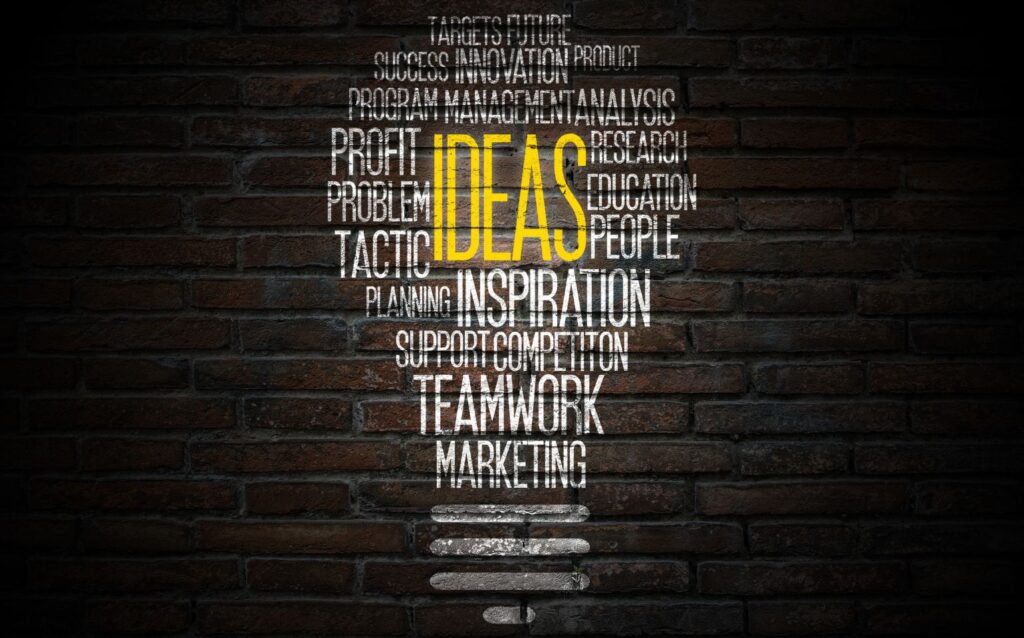
#命令文:
あなたは大学教授です。
生徒に作成してほしい新規性、有用性の高い研究論文のタイトルを5つ考えてください。
生徒は以下の{学部学科} です。
#学部学科:
(ここにあなたの学部、学科、専攻などを記入)仮案として、今回は工学部船舶海洋工学科としています。
ChatGPTの回答
もちろん、工学部船舶海洋工学科の生徒向けに新規性と有用性の高い研究論文のタイトルを5つ考えます。
以下が提案するタイトルです:1. “船舶エネルギー効率向上のための新しい動力システムの設計と評価”
2. “海洋環境保護のためのバイオディーゼル燃料の製造と応用に関する研究”
3. “無人海洋探査機の自律制御と海洋データ収集の最適化”
4. “船舶の航行安全性向上のための先進的なセンサー技術とデータ解析の統合”
5. “船舶デザインにおける持続可能な材料と製造プロセスの革新的アプローチ”
これらのタイトルは、工学部船舶海洋工学科の学生が興味を持ち、将来の研究プロジェクトとして探求できるトピックをカバーしています。どのタイトルも新しいアイデアや技術の開発に貢献できる可能性があります。
ChatGPT
この中からご自身の専攻と関係の薄いものを省き、無難なものをチョイスします。
もしも希望するようなものがなければ、上記プロンプトを何度か試してみましょう。
今回は、「無人海洋探査機の自律制御と海洋データ収集の最適化」とします。
#命令文
あなたは優秀な大学院生です。
以下の{タイトル} で論文を書くときのアウトラインを教えてください。
#タイトル:
無人海洋探査機の自律制御と海洋データ収集の最適化
(ここにあなたの希望するタイトルをコピペしてください)ChatGPTの回答
素晴らしいタイトルですね!「無人海洋探査機の自律制御と海洋データ収集の最適化」に基づいて論文のアウトラインを提供します。このアウトラインは、研究の主要なセクションとアイデアを示すためのもので、具体的な詳細は論文の内容や研究の進行状況に応じて調整する必要があります。
論文アウトライン
1. 序論
- 研究背景
- 無人海洋探査機の重要性と応用分野
- 自律制御とデータ収集の重要性
- 研究の目的と重要性
- 研究の範囲と方法論
- 論文の構成
2. 無人海洋探査機の技術概要
- 現行の無人海洋探査機の技術と制約
- 自律制御技術の進歩
- データ収集の現状と課題
3. 自律制御システムの設計
- 制御アルゴリズムの選択
- センサー技術の選定
- ナビゲーションと障害物回避の戦略
- シミュレーションと実験の設計
4. 海洋データ収集の最適化
- データ収集の効率化戦略
- データの品質向上のための手法
- データのリアルタイム処理と分析
5. 実験と結果
- 自律制御システムの実証実験
- データ収集の実施と評価
- 結果の解析と評価
6. 議論
- 研究成果の評価と意義
- 課題と改善点の議論
- 今後の研究への展望
7. 結論
- 研究の要約と重要なポイントの強調
- 研究の貢献と将来の展望
8. 参考文献
- 使用した参考文献のリスト
このアウトラインをベースにして、各セクションを詳細に埋めていくことで、論文の構造と内容が明確になり、研究が読者にとって理解しやすくなるでしょう。また、適切な図表や実験結果の示し方も検討し、論文をより魅力的にするのに役立つでしょう。
ChatGPT
このアウトラインに従って作成したらOKです。
もちろん調べるのもChatGPTにやらせてもいいでしょう。
自分の手を使わずAIに指示を出して目的を上回る成果を達成するのがプロンプトエンジニアです。
関連記事:プロンプトエンジニアになるために必要な7つのスキル
中身も思いつかない時のためのプロンプト
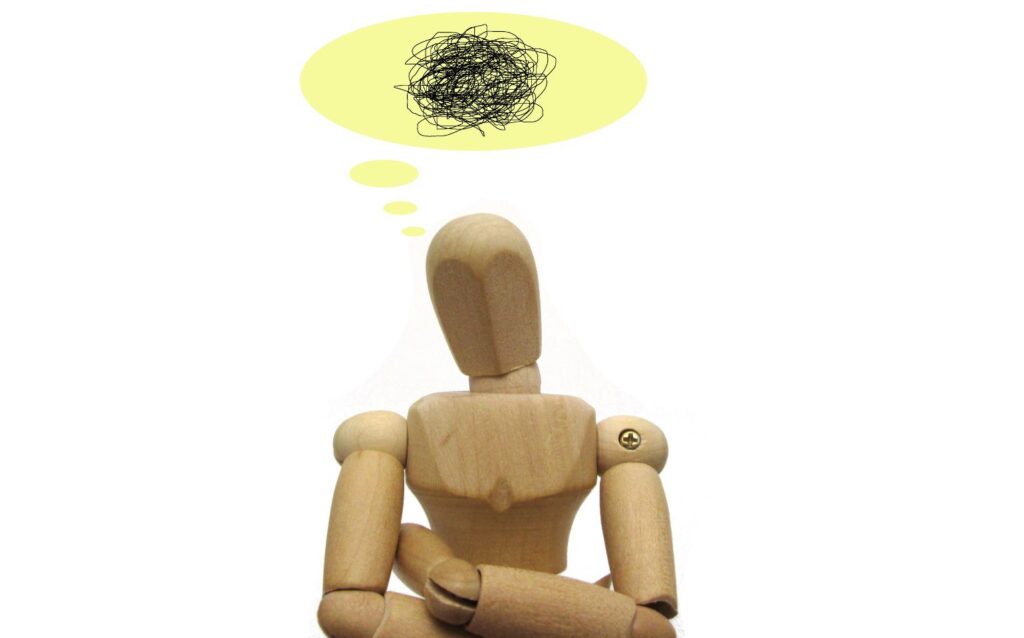
例えば、上記の論文の「4.海洋データ収集の最適化」の部分が思いつかなかったとします。
プロンプト
#命令文:
あなたは優秀な大学院生です。
以下の{アウトライン} に従って新規性、有用性の高い論文の文章生成を行なってください。
#アウトライン:
##海洋データ収集の最適化:
###データ収集の効率化戦略
###データの品質向上のための手法
###データのリアルタイム処理と分析こうすると「4.海洋データ収集の最適化」の部分だけで論文を仕上げようとしてきますが、カットしないといけない部分が生成されると思いますのでおそらく問題はないでしょう。
ChatGPTの回答
海洋データ収集の最適化に関する論文を以下のアウトラインに従って執筆します。
データ収集の効率化戦略
海洋データ収集の効率化は、海洋学や環境科学の研究において重要な課題です。効率的なデータ収集は、リソースの最適利用や環境データの精度向上に貢献します。本論文では、以下の効率化戦略に焦点を当てます。
1. センサー配置の最適化
適切な位置にセンサーを配置することで、データ収集の効率を向上させる方法を探求します。海洋の動態や特定のパラメータに合わせてセンサーの配置を最適化する手法について述べます。数値シミュレーションと実地調査の結果に基づいて、最適な配置戦略を提案します。
2. 自律型ロボットの活用
自律型ロボットは、海洋データの収集に革命をもたらす可能性があります。本論文では、ドローンや自動浮力プラットフォームなどの自律型ロボットを用いたデータ収集の方法を探究します。これらのロボットの利点と課題に焦点を当て、最適な運用戦略を提案します。
データの品質向上のための手法
高品質な海洋データは、科学的な研究や環境モデリングにおいて不可欠です。データの品質向上に関する以下の手法に焦点を当てます。
1. センサー精度の向上
センサーの精度向上は、データ品質の改善に直結します。本論文では、新しいセンサーテクノロジーの開発や既存センサーの校正方法について議論します。これにより、高精度なデータ収集が可能となります。
2. データクオリティ管理
収集されたデータの品質管理は、長期間の研究プロジェクトにおいて不可欠です。データ品質の監視と改善戦略について論じ、データの信頼性と整合性を確保する方法を提案します。
データのリアルタイム処理と分析
海洋データのリアルタイム処理と分析は、災害予測や生態系の監視などのアプリケーションにおいて重要です。本論文では、以下のポイントに焦点を当てます。
1. リアルタイムデータ処理プラットフォーム
海洋データのリアルタイム処理に適したプラットフォームやアーキテクチャについて議論します。高速データ収集と処理が可能なシステムの設計や実装に関する提案を行います。
2. データ分析アルゴリズム
収集されたデータを効果的に解析するためのアルゴリズムの開発や選定について論じます。データから有用な情報を抽出し、リアルタイムで意思決定を支援するための方法を提案します。
以上のアウトラインに基づいて、海洋データ収集の最適化に関する論文を執筆することで、新規性と有用性の高い研究成果を提供することを目指します。
ChatGPT
どうしても手直ししないといけない部分がありますが、ChatGPTの性質上仕方ありません。
関連記事:ChatGPTの仕組みを分かりやすく解説
自分もやってみた

「研究テーマが思いつかないのに無理やり論文を書く時の心理学」というタイトルの論文を作成したいと思います。
プロンプト
#命令文
あなたは優秀な大学院生です。
以下の{タイトル} で論文を書くときのアウトラインを教えてください。
#タイトル:
研究テーマが思いつかないのに無理やり論文を書く時の心理学「研究テーマが思いつかないのに無理やり論文を書く時の心理について」という論文のアウトラインを以下のように提案します。
—
1. はじめに
1.1. 背景
- 研究の重要性
- 学問的背景と現状の問題点
- 論文の目的と主題の紹介
1.2. 研究の目的
- 本研究が扱う心理的側面の概説
- 対象とするケースや事例の紹介—
2. 文献レビュー
2.1. 研究のプレッシャーに関する先行研究
- 大学院生のプレッシャーに関する研究
- 論文執筆に関する研究
2.2. モチベーションと研究テーマ選定
- 内発的・外発的モチベーションの違い
- テーマ選定の難しさと影響—
3. 方法
3.1. 研究対象
- 対象者の選定理由
- 対象者の特徴や背景
3.2. データ収集
- アンケートやインタビューの方法
- 収集期間と方法
3.3. データ解析
- 解析手法の選定理由
- 使用したツールやソフトウェア—
4. 結果
4.1. データの概要
- 応答者の特徴や背景情報
- 研究テーマ選定の難しさに関するデータ
4.2. 主な発見
- 心理的要因や影響
- テーマ選定の際の感情や考え方—
5. 考察
5.1. 結果の意味
- 発見された心理的側面の意味
- 先行研究との関連性や差異
5.2. 限定性と提案
- 本研究の限定性
- 今後の研究方向や提案—
6. 結論
6.1. 本研究の要約
6.2. 今後の研究や対策への提言—
7. 謝辞
—
8. 参考文献
—
このアウトラインは一例に過ぎません。実際の論文執筆時には、具体的な内容や研究の進行に応じて調整が必要です。
ChatGPT
無論、中身まで書いてもらいます。
1. はじめに
1.1. 背景
研究の重要性
近年、大学院生や研究者たちの間で研究テーマの選定に関するプレッシャーが増してきたことが指摘されています。このプレッシャーがどのような心理的要因に起因しているのか、そしてそれが研究の質や研究者の心理健康にどう影響しているのかは、学問の進展や研究者の生産性にとって非常に重要な問題となっています。
学問の背景と現状の問題点
学問の歴史を通じて、研究者は新しい発見や理論を求められてきました。しかし、情報の洪水の中でオリジナルなテーマを見つけることの難しさや、社会的・学術的な期待とのギャップにより、研究者の心理的ストレスが増加しているとの報告がある。
論文の目的と主題の紹介
この論文は、「研究テーマが思いつかないのに無理やり論文を書く時の心理」に焦点を当てています。具体的なケースや事例をもとに、その背景にある心理的要因や影響を深く探ることを目的としています。
1.2. 研究の目的
本研究が扱う心理的側面の概説
本研究では、研究テーマの選定に関するプレッシャーやその他の外部・内部要因が研究者の心理に与える影響を中心に検討します。特に、研究のモチベーション低下、焦燥感、自己効力感の喪失などの心理的変動を重点的に取り上げます。
対象とする事例や事例の紹介
本研究の対象としては、複数の大学院生や初期の研究者を対象にしたアンケートやインタビュー結果を基にしています。特に、テーマ選定に1年以上かかったケースや、テーマ変更を経験したケースなど、研究テーマ選定の難しさを強く感じた事例を中心に分析します。
2. 文献レビュー
2.1. 研究のプレッシャーに関する先行研究
大学院生のプレッシャーに関する研究
近年の研究によれば、大学院生は学位取得のプレッシャーや研究テーマの選定、指導教員との関係など、多岐にわたる要因により精神的なプレッシャーを感じているとされている(仮、 2020)。特に、研究テーマの選定に関しては、自身の興味や専門分野とのマッチング、将来のキャリア形成に対する不安が影響しているとの報告がある(仮、 2021)。
論文執筆に関する研究
論文執筆の過程におけるストレスやプレッシャーも注目されている。研究者の中には、情報の整理や論文の構造作成、言語的表現など、執筆に関連する複数の要因がストレス源となっていると指摘する者もいる(仮、 2019)。また、執筆のプレッシャーが研究者の創造性や生産性に悪影響を及ぼしている可能性が示唆されている(仮、 2022)。
2.2. モチベーションと研究テーマ選定
内発的・外発的モチベーションの違い
モチベーションには、内発的モチベーションと外発的モチベーションという二つの主要なタイプがある。内発的モチベーションは、自分自身の興味や楽しさからくる動機付けであり、研究への情熱や興奮を生む要因となる(仮、 2018)。一方、外発的モチベーションは、報酬や罰、他者の期待など外部からの要因による動機付けであり、しばしばプレッシャーとして研究者に影響を及ぼす(仮、 2019)。
テーマ選定の難しさと影響
研究テーマの選定は、研究者のキャリアや学術的な貢献に大きな影響を及ぼす。テーマ選定の難しさは、先行研究の存在、オリジナリティの要求、また研究リソースの制限など、多くの要因に起因している(仮、 2020)。このテーマ選定のプレッシャーが、研究者のモチベーション低下や焦燥感を引き起こすことも示されている(仮、 2021)。
※参考文献名や著者名は仮のもので、実際の文献や研究に合わせて変更する必要があります。
まとめ
全文やらせるのはモラル的によくないかもしれませんし、文献も全て架空のものですが、かなり手助けになるのではないでしょうか。
このような役に立つプロンプトがたくさんあるので、プロンプトパークをぜひご覧ください。
関連記事:プロンプト文例集「プロンプトパーク」の使い方・おすすめの人を紹介!













